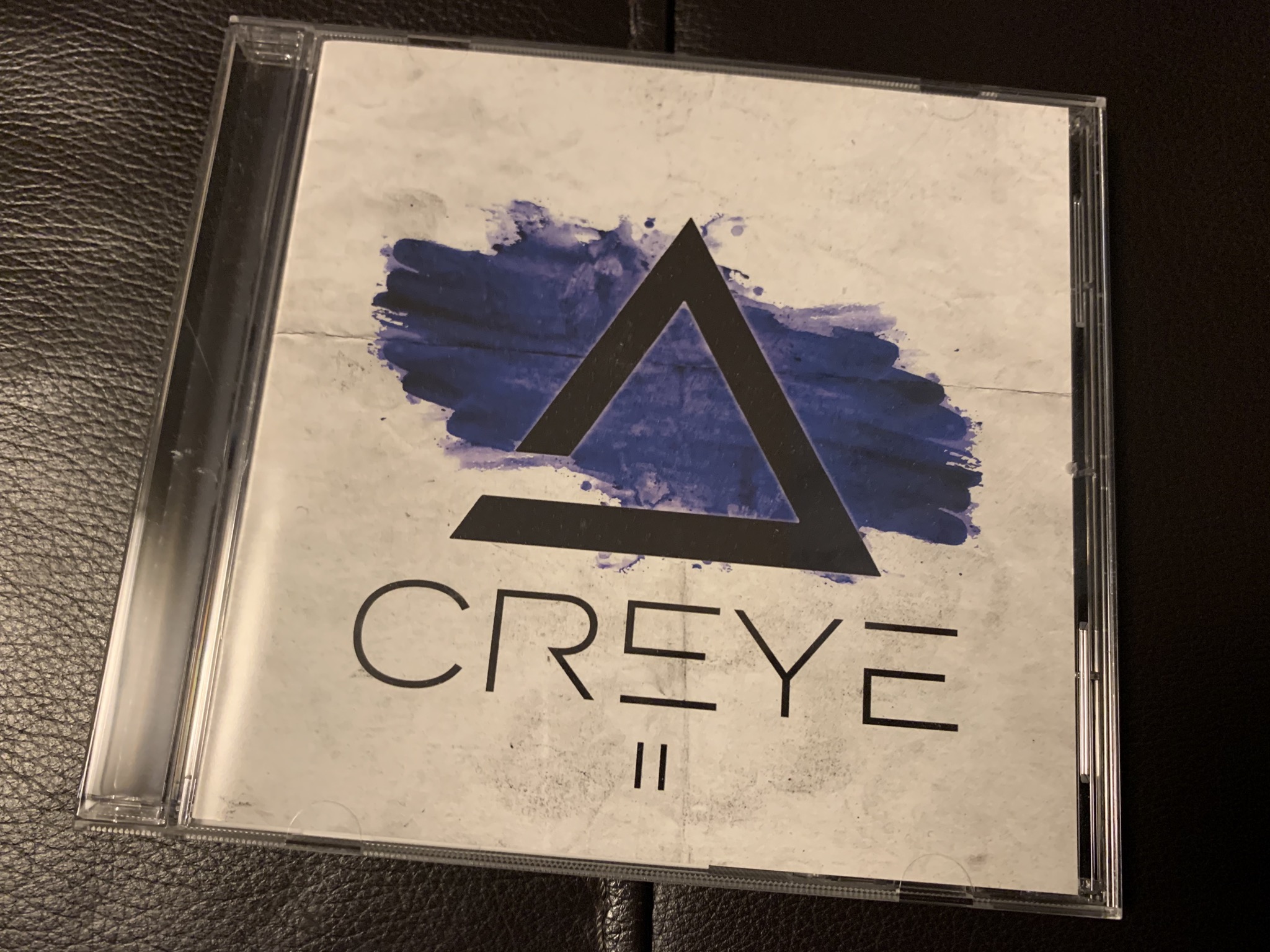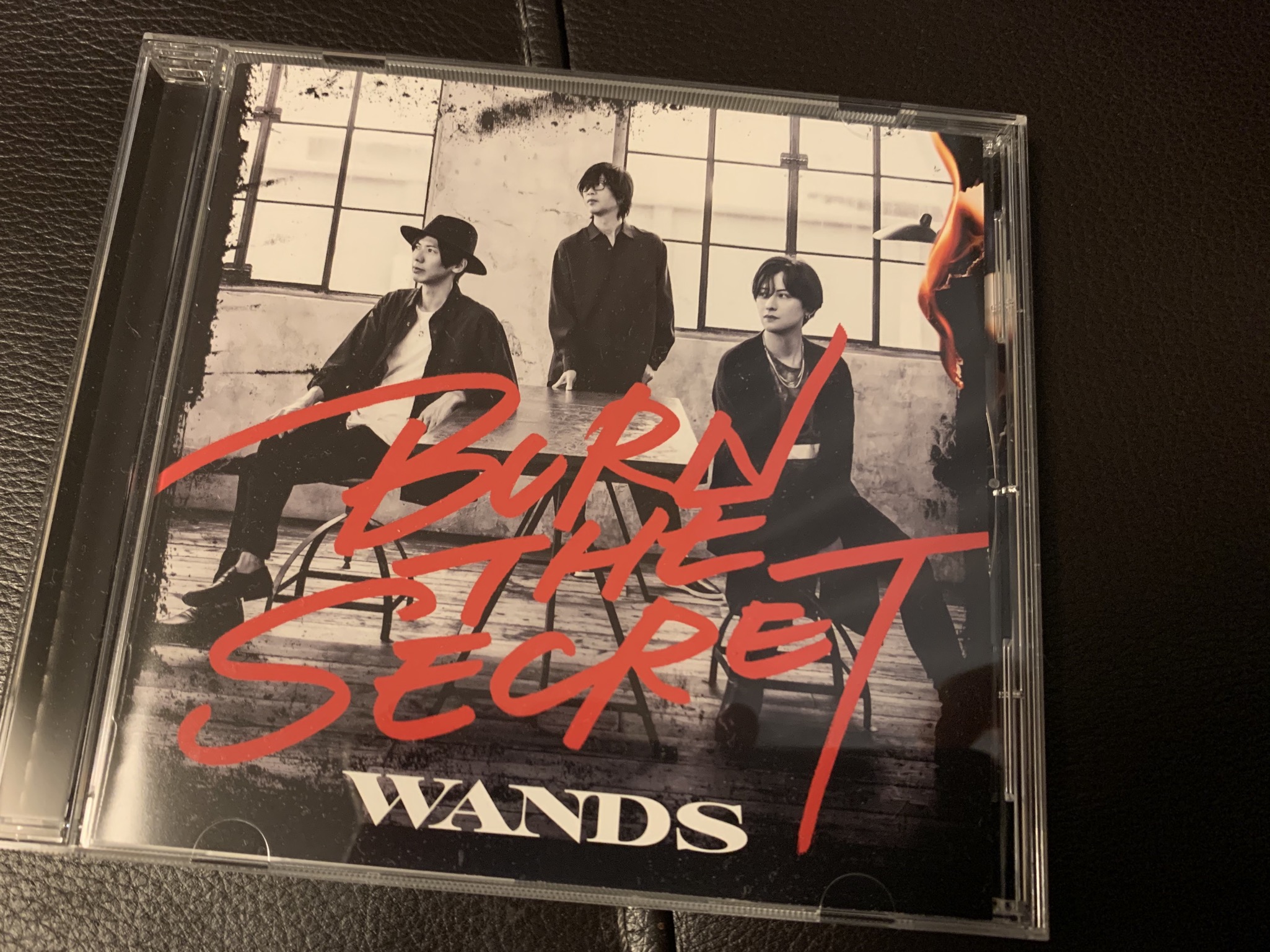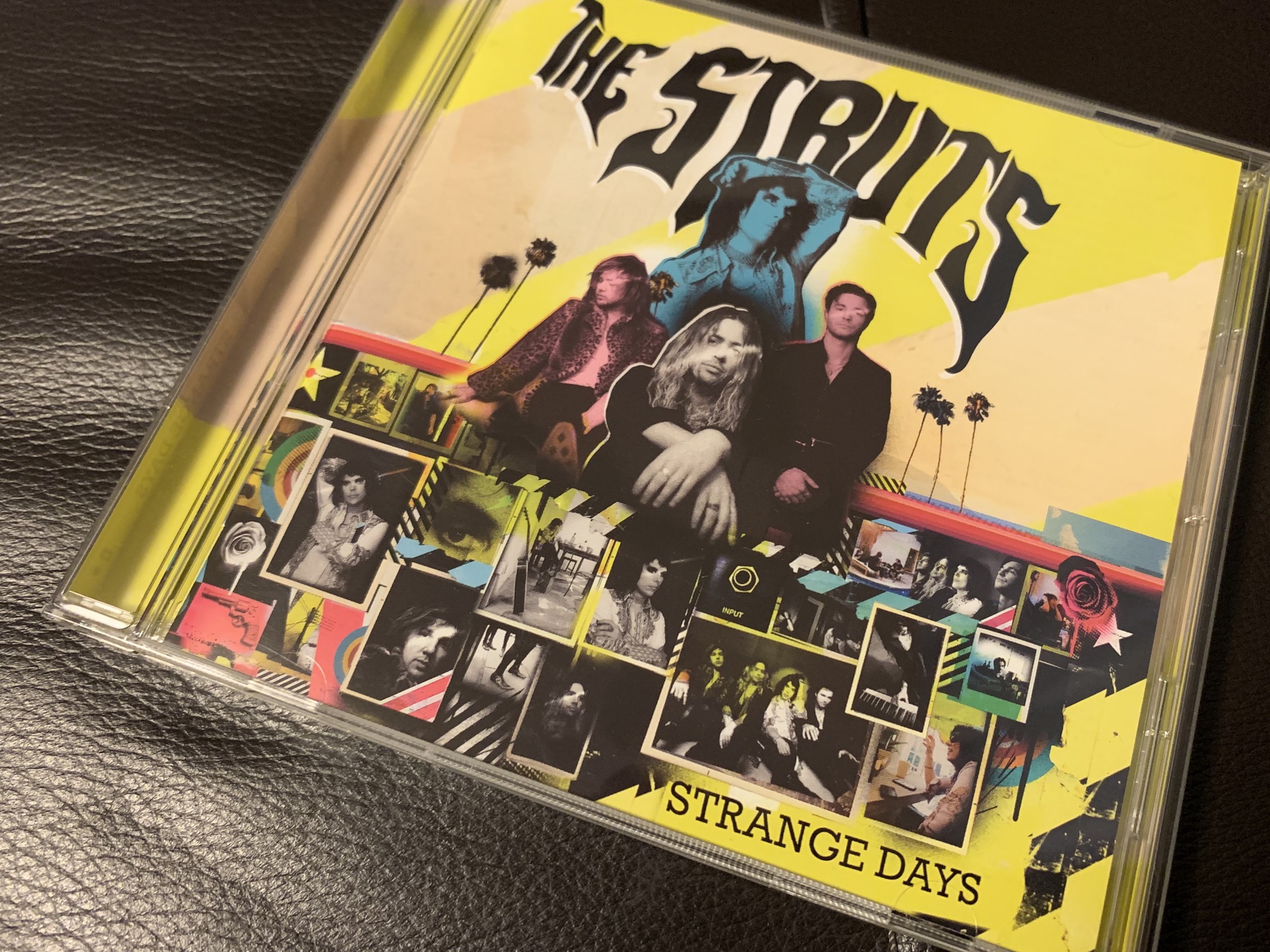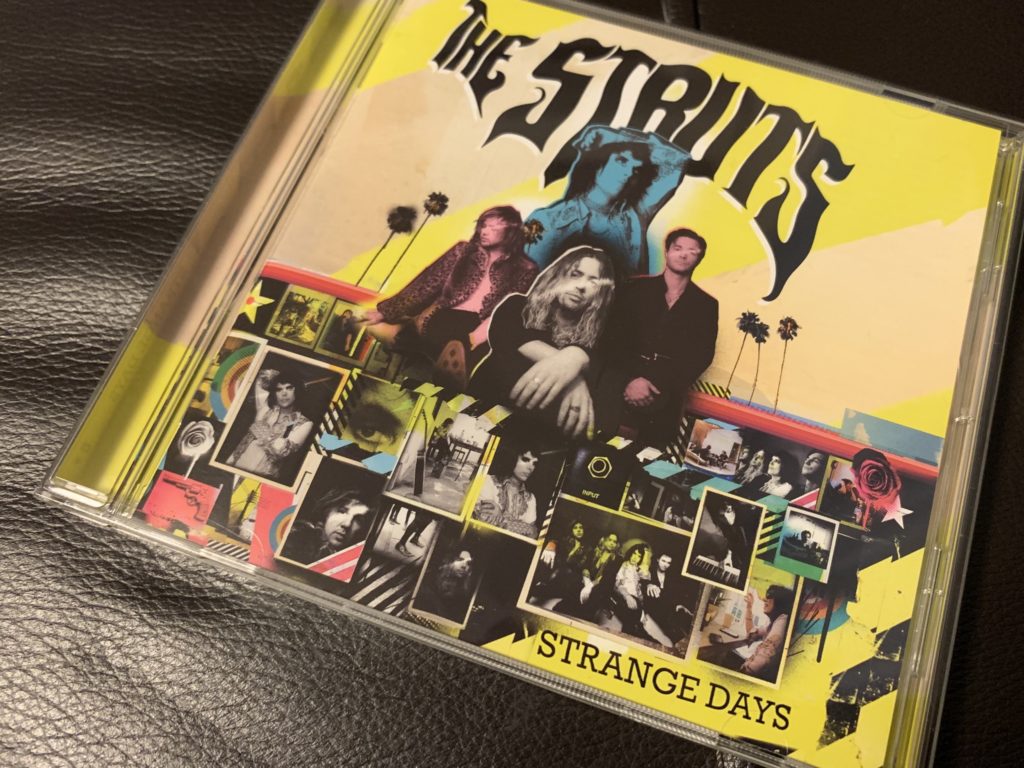BAND-MAIDの1stフルアルバム『Just Bring It』が素晴らしい
あれは冬の日曜の昼下がりのことでした。
ソロキャンプ後に家の自室でゴロゴロしていたら、友人が先日RTしていたバンド、BAND-MAIDの記事が目に止まりYouTubeでチェックしてみたところ、すっかり気に入ってしまった私は、そろそろ暮れなずみそうな時刻に部屋を飛び出して愛車に乗り込み、最寄りのツタヤでBAND-MAIDのアルバムをありったけ借り占めてきました。
その中の一枚が、彼女たちの1stフルアルバム『Just Bring It』でした。
友人からまずはこのアルバムから聴いてみるのをおすすめされた私は、素直にこのアルバムから聴き始めて、すんなりと彼女たちのハードロックの魅力に取り憑かれることになったのでした。
ところで、BAND-MAIDとは全然関係ない思い出話ひとつ、いいですか。
『Just Bring It』は日本語に訳すと「かかってこい」という意味になるそうですが、この言葉を聞くとワンオク初の大阪城ホール公演を観に行ったときのことを思い出します。バンドのMC中に、「もっと来んかい!」と叫んだお客さんがいたことを。大阪らしいなあと笑っちゃったんですけど、それに対するワンオクからの反応がまた面白かったんですよね。
「はああ???めちゃくちゃ行ってるし!!!」
かかってこい、などと煽ると、当然ですけど強い反発が返ってきます。それに負けずに応えてみせる、という気骨や気概が込められたタイトルなのでしょう。
BAND-MAIDは、このアルバム以前にインディーズでEPを二枚、メジャーでEPを一枚発表しているのですが、主に編曲のみで、自身による作詞や作曲はごく一部でした。インタビュー記事を読んだところによると、以前から作詞作曲はしていたのだが提出した曲がことごとくボツだったそうで、自分たちの曲をもっとたくさん世に出したいと密かに創作意欲を燃やしていたようです。
作詞作曲にボツを喰らいまくった悔しさをバネに飛躍したのか、この『Just Bring It』では収録曲全13曲中9曲がバンドにより作曲され、11曲が作詞されています。押さえつけられていた反動の爆発か、バンドによる楽曲の出来が目を瞠るほど素晴らしい。
序盤からアグレッシブで掴みの強い曲が続き、中盤でややポップかつセンチな曲が並んだかと思えば、終盤でまたギアを上げて強烈な曲をガツンとかましてくる。痺れる構成です。収録曲数は多いんですけど、再生時間が短いので冗長さがなく濃密で、一枚があっという間です。
外部ライターから提供を受けている楽曲も劣らず素晴らしいんですけど、バンドによる楽曲が強力すぎて生半可な曲では選曲の段階で淘汰されて生き残れないので、それも当然の帰結。相乗効果。
前EPに収録されていた唯一のバンドによる作曲”alone”でその才能の片鱗をのぞかせていましたけど、ここに来て一気に開花させてきました。
やっぱり、バンドたるもの自分たちが歌いたい曲を自分たちで書いて自分たちで演奏すべし、という思いを新たにしましたね。
決して外部ライターがだめというわけではありません。最終的にはある一定以上の水準が保たれた高品質な楽曲に仕上がってくるでしょう。しかし、自分たちならではの個性はどうしても薄れてしまいますし、自分たちで書き上げたものではない以上どれだけ気合を入れても自作の熱量と思い入れには敵いません。ソツはないかもしれませんが、没個性で面白味に欠けてしまうんですよね。
多少荒削りでも、個性丸出しの面白い音楽を聴きたい。
そんなささやかな願いを、BAND-MAIDは1stフルアルバムでいきなり叶えてくれました。
荒削りどころか、豪快にぶっ飛んだキャッチーなハードロックで。
かかってこい。ファンからの要求がエスカレートするのも、望むところなのでしょう。真正面から応えてみせる。自分たちで書いた曲で。
そして、続く2ndアルバム『WORLD DOMINATION』、3rdアルバム『CONQUEROR』で、ファンの期待を上回る断固たる決意のほどを見せつけてくれるのでした。