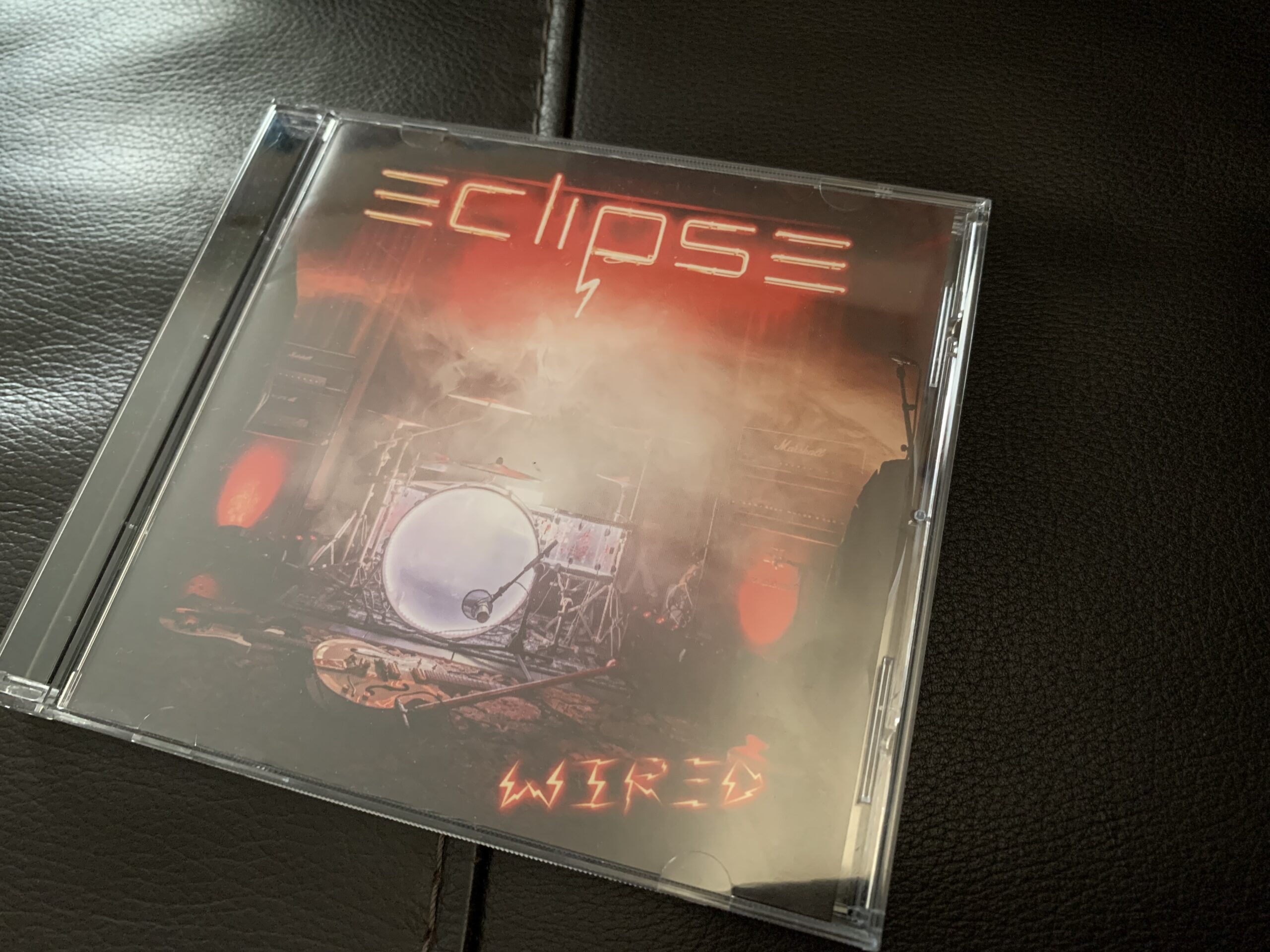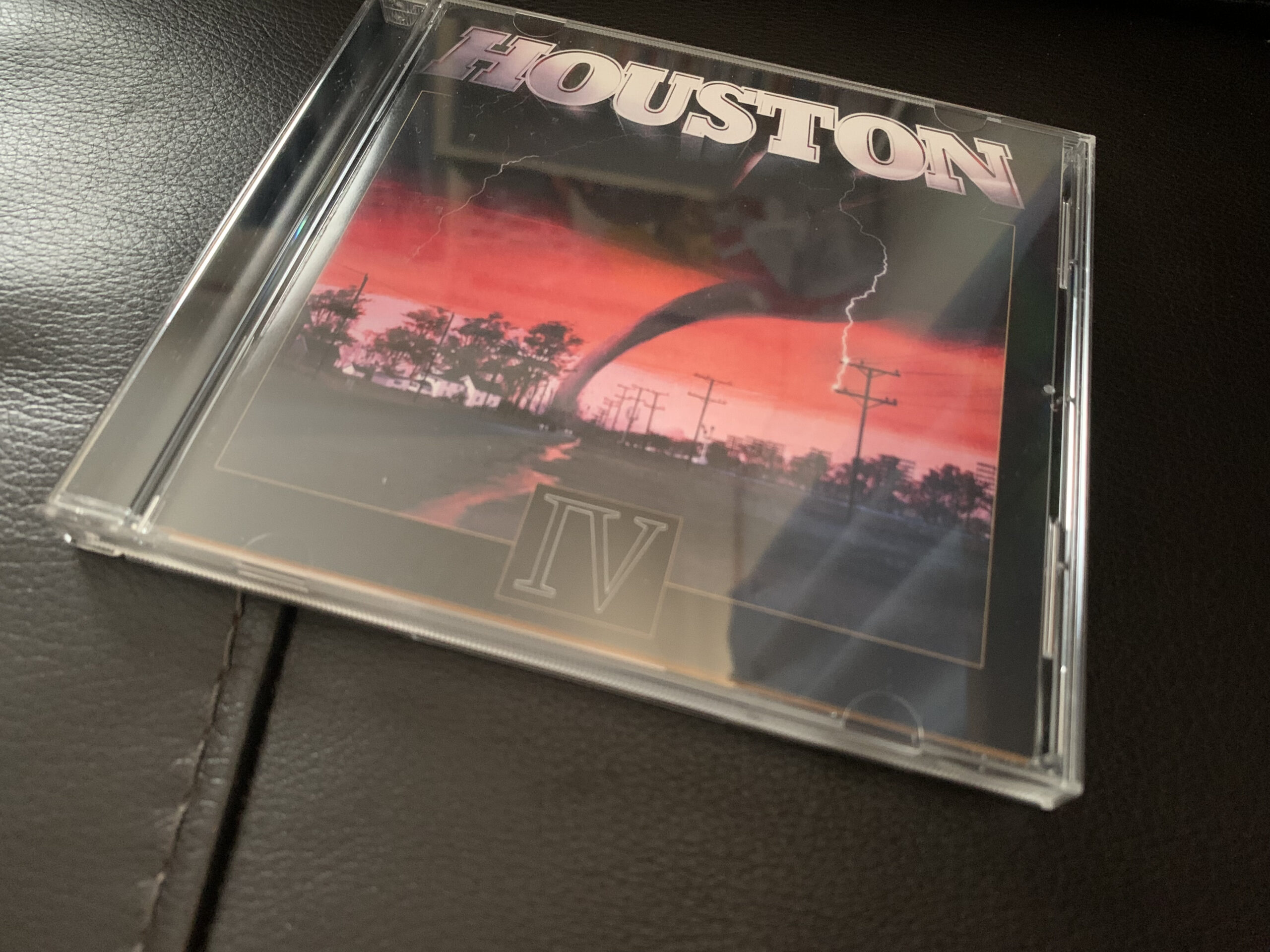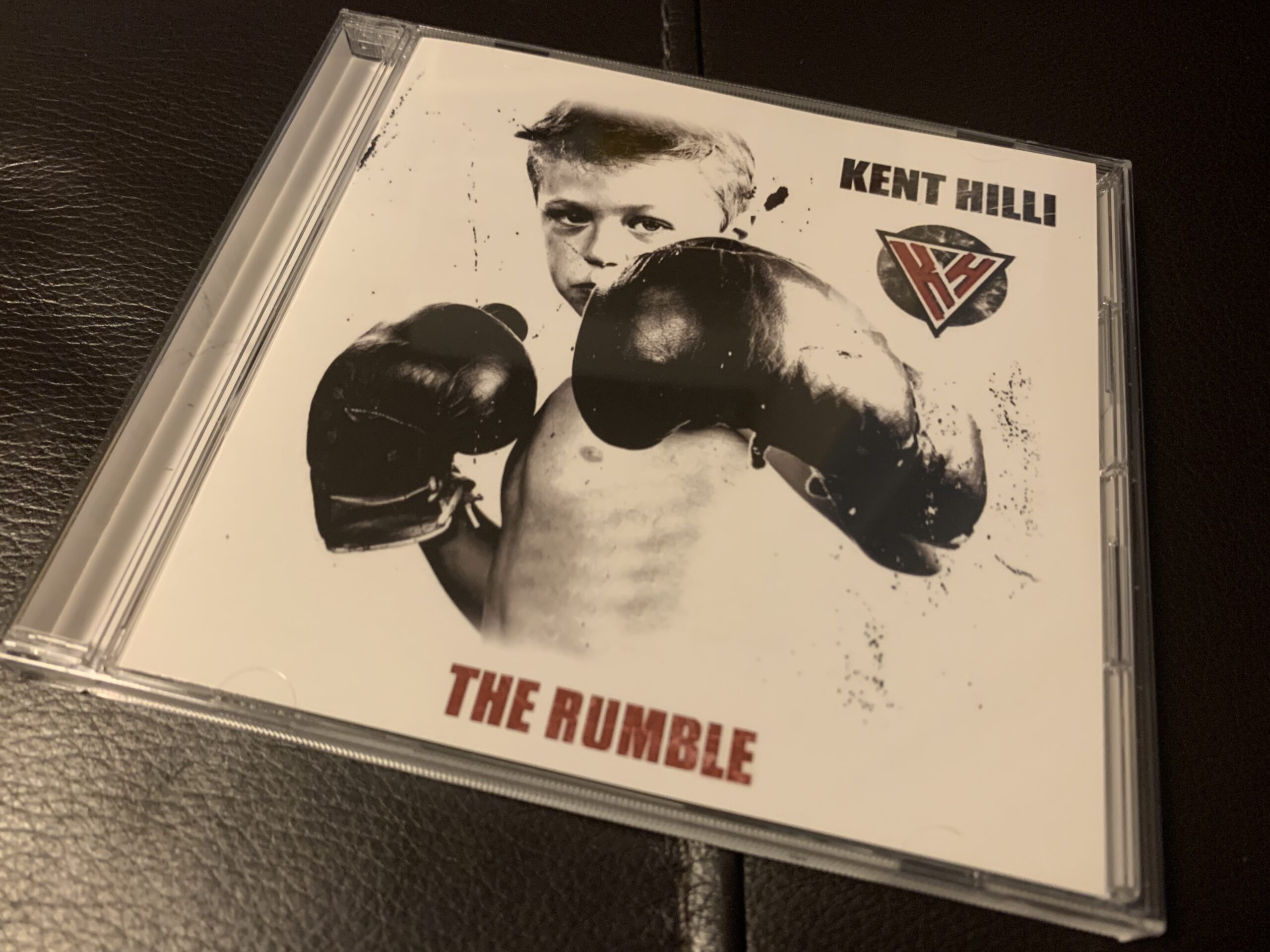Art Of Illusionの1stアルバム『X Marks The Spot』を聴いた感想
Art Of Illusionは、ともにスウェーデンのメロディアス・ハードロック・バンドであるGrand IllusionのAnders RydholmとWork Of ArtのLars Safsundが手を組んだプロジェクトで、『X Marks The Spot』はそのプロジェクトのデビュー・アルバムです。
日本盤の発売日が2021年の2月3日なので、すでに発売から約一年が経過しようとしています。
今更感半端ないですが、新年2022年が明けてから、部屋でゴロゴロと読書をしながら2021年の新譜を聴き直して振り返っていたら、Art Of Illusionのアルバムに(やっぱり良いなぁ)と聴き入ってしまいました。
数曲で外部ライターが作詞していたりAndersとLarsが共作していますが、ほとんどの楽曲はAndersがひとりで手掛けているので、音楽性は基本的にはGrand Illusionを踏襲した、計算し尽くされた構築美の枠組みの中でキーボードやギターが躍動するメロディアス・ハードロックです。
本作に収録されているリードギターは絶品ですね。曲によってプレイヤーは様々ですが、ときにサスティーンを魅惑的に響かせ、ときに挑発的な速弾きで刺激して。そのツボを知り尽くした音色に思わず(うおぉ、これこれ!)と顔をほころばせたファンも多いでしょう。
Larsの歌声は相変わらず素晴らしいですね。Work Of ArtやLionvilleですでに彼の歌声を聴いている人からしたら言わずもがなのことですが、軽やかで爽やかながらパンチもあるハイトーンは耽美的です。
コーラスワークも素晴らしいですね。Grand Illusionを彷彿とさせる、天高く舞い上がらんばかりのコーラス。最高に気持ちいいです。バック・ヴォーカルにはAndersと長年の付き合いのPer Svenssonが参加し、プロデュースとアレンジもAndersとLarsが共同で手掛けているので、当然といえば当然の帰結でもあります。
また、このプロジェクトの新要素として、歌劇のように振り幅が大きく劇的な展開を見せる曲が飛び出してきたりします。歌劇のような展開というと、多くの人の頭にパッと思い浮かぶのはQueenやRobby Valentineでしょう。
あまり大仰すぎず、あくまでも楽曲を彩るひとつの要素、というバランスの見事なさじ加減なので、あまり派手な演出はちょっと苦手だという人でも身構えずにすんなり聴けると思います。
ボーナストラックの”No Goodbyes”がめちゃくちゃいいので、もしこれから買うのであれば絶対に日本盤がおすすめ。「なぜこの名曲が日本盤のみのボーナストラックなのか意味不明ランキング」を作成したら、トップ10入りは堅いレベルの曲です。
最近は収録曲の別バージョンばっかりで、こういう美味しいボーナストラックがめっきり減ってしまいました。
このプロジェクトでGrand Illusionの存在を知って、遡る人もいるんでしょうね。
Grand Illusionの過去作を掘り下げるのは、未来からのタイムトラベラーにまだ誰の手もついていない鉱山を教えてもらうようなものです。
もう美味しいところはあらかた聴き尽くしたと思っていても、それはたんなる勘違いで、世の中にはまだまだたくさん素晴らしい音楽が眠っていて、掘り起こされるのを今か今かと待ちわびているのです。