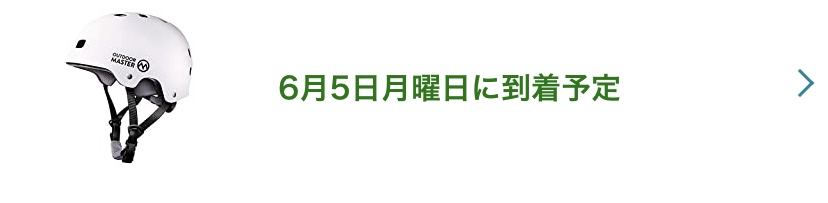8年間使い込んだ愛機キヤノンEOS 8000Dの損耗に気がついて、デジタル一眼カメラの買い替え欲がにわかに熱を帯びてきた
先日、母を連れて山梨県の北杜市でお花見してきました。
眞原桜並木をぐるっとひと通り歩いてきて疲れたので、木陰のベンチに座って小休止しようとした時に、デジタル一眼カメラを持っていた右手の人差し指に引っ掛かりを覚えました。
うん?なんだ?今までこんな感触なかったよな…?
で、よくよく見てみて気がついたのが、サムネの画像のグリップの部分の浮きです。
初陣が2016年の6月下旬で、約8年間で22000ショット以上撮ってきてますからね。
そりゃ損耗もしてくるでしょう。
前に使っていたα33の写真も今見返してみても充分綺麗で、それは今使っているEOS 8000Dに関しても同じなのですが、まだまだ使えるとは思いつつも、こういった損耗に気がついてしまうと(そろそろ買い替えか…?)という気持ちが頭をもたげてしまうのもまた事実。
そんな自分のカメラ観ですが、あんまり高すぎると予算的に買えないというのと、天気が悪い時や砂埃が舞いそうなところだと想像がつく場所には、カメラを濡らしたり汚したりしたくないがために持ち出さずに箱入り娘にしちゃいそうなので、コスパ重視で気兼ねなく持ち出したい派です。
憧れ枠と実用枠とおしゃれ枠。家電屋で次期愛機候補の三台を触って比べてきたので、そんなカメラ観に基づいた使用感をメモしておきます。
Canon EOS RP 24-105mmキット
まずはこちら。コスパ最強フルサイズミラーレス。撒き餌レンズならぬ撒き餌ボディ。
APS-C機入門機並みの値段で新品でフルサイズが買える唯一のカメラ。性能的には最新機種に見劣りしても、とにかく安く憧れのフルサイズミラーレスが欲しいならこれ一択。
外装に使われている素材が一体なんなのか、手触り肌触りがとにかく最高。ずっと触っていたくなる。愛車のステアリングや傘の取手など、よく手で触るところの素材を全部これと同じに変えたくなるほど。
ダイヤルのクリック感もカチッとしてて気持ちいい。
EOS R10もだが、バッテリーがEOS 8000Dと共通なのはでかい。
ただ、フルサイズ用のRFレンズは高すぎるので、このキットレンズ一本で頑張らざるを得なくなるのが勿体無いような…。
Canon EOS R10 18-150mmキット
コンパクトなEOS RPよりもさらにひと回り小型軽量なボディが魅力。
18mm〜150mmまでカバーするキットレンズ、(EOS 8000D比)爆速の瞳AFなど、取り回しのしやすさと使い勝手の良さが魅力的。
RF-Sレンズの少なさが泣きどころだったが、先日タムロンとシグマがRFレンズ供給を発表し、この弱点が魅力に転じる可能性が出てきた。
このセットを買えば、現状とほぼ変わらない撮影システムを手軽に揃えられるのは大きい。実用性最高。
Nikon Z fc 16-50mmキット
おしゃれでかっこいい見た目と、軽量コンパクトな作りと、マニュアル撮影しやすそうなダイヤル操作系が魅力。
ただ、望遠で撮ることが好きなので、望遠端が50mmまでしかないのが物足りなくなって、望遠ズームを一本買い足すことになりそう。
あと、グリップがないのでホールド性がやや心許ない。大きなレンズをつけるとバランスが崩れデザイン面の魅力も後退してしまうかも。
グリップなどのアクセサリー追加で自分好みの仕様にカスタムしたくなり、迷走したり一周回って素に戻るなど、苦労が予想される。厄介なのは、それもまた楽しいってこと。